お電話でご相談
「受診するほどではないかも…」「自分では判断できないかから受診や検査について詳しく聞きたい」という方は、どうぞお気軽にお電話ください。経験豊富な職員が、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えいたします。
電話によるお問い合わせ電話番号:048-783-2637
受付時間:8:45~18:00
些細なことでも構いませんので、気になることがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
詳細な検査を必要と判断した場合は、スムーズに検査のご案内をさせていただきます。
突然の吐き気や嘔吐、激しい腹痛、下痢に襲われていませんか?発熱や倦怠感を伴うこともあります。これらの症状は、もしかすると食中毒のサインかもしれません。

「受診するほどではないかも…」「自分では判断できないかから受診や検査について詳しく聞きたい」という方は、どうぞお気軽にお電話ください。経験豊富な職員が、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えいたします。

検査内容についてご理解いただけましたら、お電話で直接ご予約いただくことも可能です。
ご希望の日時や、その他ご要望などございましたら、お気軽にお申し付けください。
食中毒とは、細菌やウイルス、あるいは有害な化学物質などが付着した飲食物を摂取することで引き起こされる健康障害の総称です。主な原因は細菌性、ウイルス性、自然毒、化学物質によるものに分類されます。
食中毒の原因は多岐にわたります。代表的なものとしては、カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O157などの細菌、ノロウイルスやロタウイルスといったウイルスが挙げられます。これらの微生物は、加熱不足の肉や魚介類、生卵、不適切な取り扱いをされた食品などを介して体内に侵入します。また、キノコやフグなどの自然毒、農薬や洗剤などの化学物質が原因となるケースも存在します。特に夏場は細菌が繁殖しやすく、冬場はウイルス性の食中毒が増加する傾向があります。
食中毒の症状は、原因となる物質や摂取量、個人の免疫力によって異なります。一般的に、原因となる飲食物を摂取してから数時間から数日後に症状が現れることが多いです。初期症状としては、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などが挙げられます。症状が進行すると、脱水症状や発熱、倦怠感、頭痛などを伴うこともあります。重症化すると、意識障害やけいれんを引き起こし、命に関わる場合もあるため、早期の診断と治療が重要です。
食中毒の診断は、患者様の症状や飲食歴の聴取、身体診察に加え、必要に応じて便の細菌検査やウイルス検査などを行います。特に、集団発生の場合には、原因となる食品の特定も重要となります。当クリニックでは、問診を丁寧に行い、症状と状況を総合的に判断し、適切な診断に努めます。
食中毒の治療は、症状の緩和と原因菌の排出が中心となります。下痢や嘔吐による脱水を防ぐため、水分補給が非常に重要です。経口補水液などでこまめに水分を摂取しましょう。症状に応じて、吐き気止めや整腸剤、解熱剤などが処方されることもあります。自己判断で市販の下痢止め薬を使用すると、原因菌の排出を妨げる可能性があるため、医師の指示に従うようにしてください。安静を保ち、消化の良い食事を心がけることも大切です。
食中毒において手術療法が適用されることは通常ありません。しかし、重症化し、腸穿孔などの合併症を引き起こした場合には、緊急で手術が必要となる可能性もごく稀にあります。手術が必要な場合には、同法人こうのす共生病院や他医療機関をご紹介いたしますのでご安心ください。

「受診するほどではないかも…」「自分では判断できないかから受診や検査について詳しく聞きたい」という方は、どうぞお気軽にお電話ください。経験豊富な職員が、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えいたします。

検査内容についてご理解いただけましたら、お電話で直接ご予約いただくことも可能です。
ご希望の日時や、その他ご要望などございましたら、お気軽にお申し付けください。
丁寧な診察と的確な診断
豊富な経験を持つ専門医が、患者様の症状を丁寧に評価し、正確な診断を行います。患者様のお話をじっくり伺い、不安を解消できるよう努めています。

患者様一人ひとりに合わせた治療計画
保存療法から手術療法まで、幅広い選択肢の中から最適な治療法をご提案します。患者様の状態やご希望を尊重し、納得のいく治療を選択できるようサポートいたします。

駅チカでアクセス便利
大宮駅西口から徒歩3分ですので、通院しやすい環境です。お仕事帰りや買い物ついでにも、お気軽にお立ち寄りいただけます。
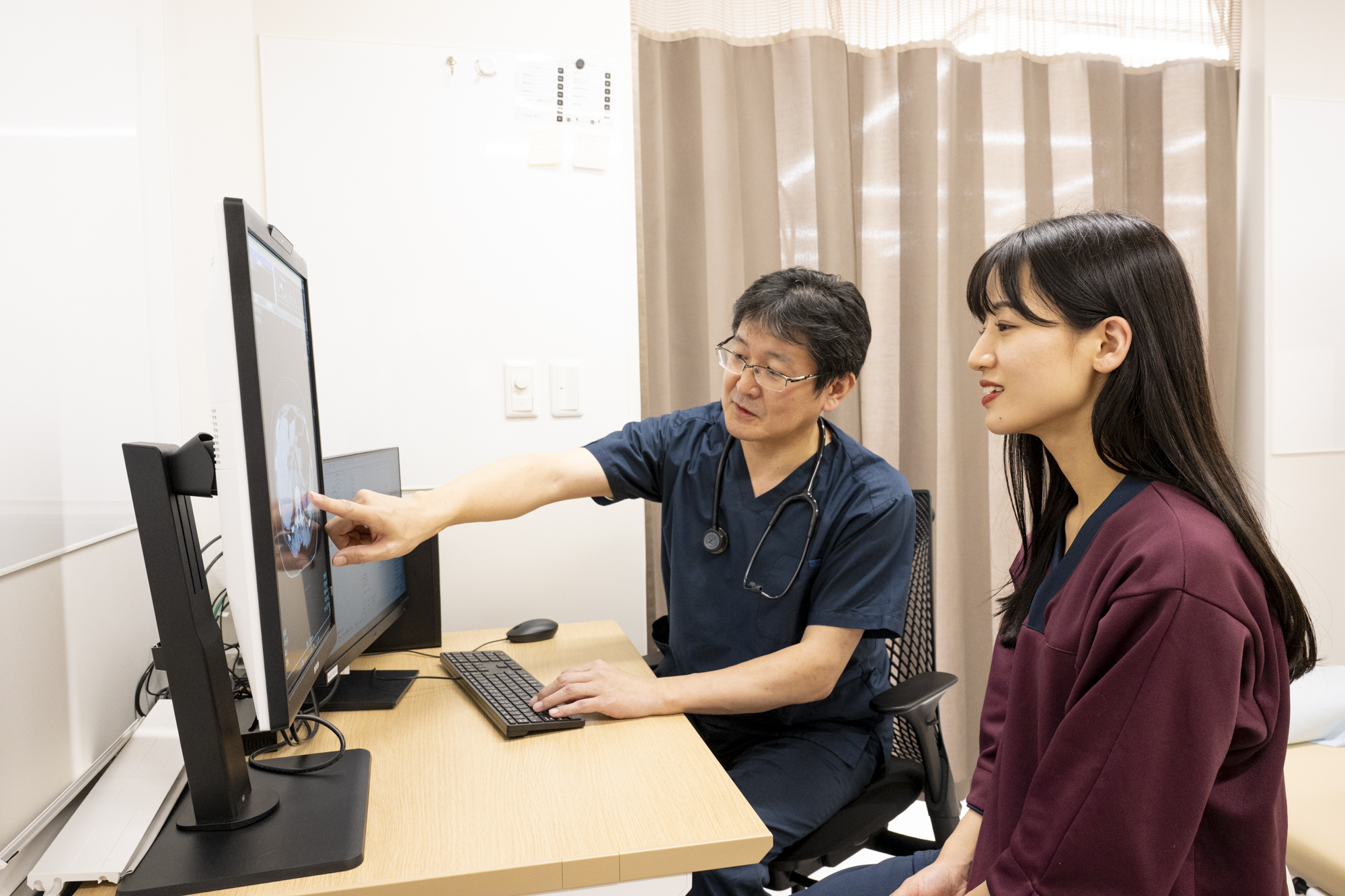
食中毒の症状は、時に急速に悪化することがあります。特に、小さなお子様や高齢者、持病をお持ちの方は、脱水症状が重篤化しやすい傾向にあります。症状が現れた際には、自己判断せずに、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。早期に適切な治療を開始することで、回復を早め、重症化を防ぐことができます。
当院では、皆様の健康をサポートするため、内科・消化器内科のご予約を承っております。
「胃が痛い…」「血便が出る…」「健康診断で指摘された…」という方も、「受診するほどではないかも…」と思っている痛みや不調も、早期の対応が回復のカギになることがあります。どんな症状でも、まずはご相談ください。当院では、一人ひとりの声に耳を傾けた丁寧な整形外科診療を心がけています。
患者様のご都合に合わせて、以下の3つの方法でご予約いただけます。
「受診するほどではないかも…」「自分では判断できないかから受診や検査について詳しく聞きたい」という方は、どうぞお気軽にお電話ください。経験豊富な職員が、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えいたします。
電話によるお問い合わせ電話番号:048-783-2637
受付時間:8:45~18:00
些細なことでも構いませんので、気になることがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
詳細な検査を必要と判断した場合は、スムーズに検査のご案内をさせていただきます。

検査内容についてご理解いただけましたら、お電話で直接ご予約いただくことも可能です。
ご希望の日時や、その他ご要望などございましたら、お気軽にお申し付けください。
「受診するほどではないかも…」「自分では判断できないかから受診や検査について詳しく聞きたい」という方は、どうぞお気軽にお電話ください。経験豊富な職員が、皆様の疑問や不安に丁寧にお答えいたします。
電話によるお問い合わせ電話番号:048-783-2637
受付時間:8:45~18:00
ご予約の際には、以下の情報をお伺いいたしますので、あらかじめご了承ください。
・お名前
・生年月日
・ご連絡先電話番号
・ご希望の検査日時(いくつか候補日をお知らせいただけるとスムーズです)
・健康保険証の情報
・現在の症状や、健康診断での指摘事項など
・現在の症状や、健康診断での指摘事項など

ご都合の良い時間に、Webサイトから整形外科のご予約が可能です。以下のボタンより、予約フォームへお進みください。
Web予約はこちら