コラム
腫瘍マーカーとは? ①基礎知識編
腫瘍マーカーはどうやって検査するの?
腫瘍マーカーの検査方法は、採血です。
通常の健康診断や人間ドックと同じように腕から血液を採取します。
その血液を分析することで、腫瘍マーカーの値を測定します。
- 採血時間:数分程度
- 結果が出るまで:数日〜1週間前後
- 注意点:空腹時でなくても検査は可能。ただし健診項目によっては空腹時採血となります。
つまり、オプション検査として気軽に追加できるのが特徴です。
今回はそんな腫瘍マーカーの「基礎知識編」をお送りします!
腫瘍マーカーでできること・できないこと
できること
・がんの可能性を知る手がかりになる
・がんの治療効果や再発の有無を確認する目安になる
できないこと
・腫瘍マーカーだけで「がんかどうか」を確定すること
・必ずしも早期がんを見つけられるわけではない
つまり、腫瘍マーカーは “補助的な検査” であり、画像検査や内視鏡検査と組み合わせることで真価を発揮します。
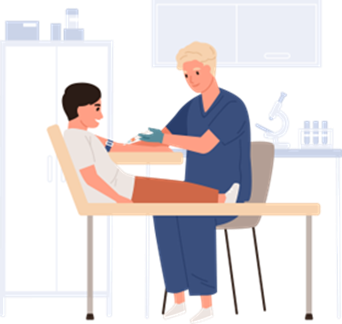
結果の見方と注意点
・「数値が高い=がん」ではありません。炎症や良性疾患、喫煙などでも上昇します。
・「数値が正常=安心」ではありません。がんがあっても数値が上がらない場合があります。
腫瘍マーカーは単独で診断を確定するものではありません。
炎症や良性疾患、喫煙習慣などでも上がることがあるため、数値だけで判断することはできません。数値が高かったから、すぐにがんというわけではないので、必要に応じて追加の検査を行い、総合的に判断します。逆に数値が正常でも、症状や画像検査で異常があれば精密検査が必要です。

第1部まとめ
腫瘍マーカーは「がんを見つける魔法の検査」ではなく、健康を守るためのヒントを与えてくれるツールです。
健康診断や人間ドックに取り入れることで、自分の体をより深く知るきっかけになります。
次回の第2部では具体的な腫瘍マーカーの種類と男女別おすすめ検査について詳しくお話しします。
ぜひそちらもご覧になって、一緒に未来の健康をデザインしていきましょう!
当院では、健診・人間ドックのオプションから腫瘍マーカーを選択いただけます。
健診・人間ドックのオプションはこちら